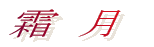
慌ただしいランチタイムもピークを過ぎて、店内はなんとなく午後のまったり感が漂っている。
サンジはテーブルセッティングを直しながら、雨の匂いに誘われるようにふと窓の外を眺めた。
先ほどまで降っていた秋雨も今は止み、庭の緑が一層色濃く輝いて見える。
このまま夜は、晴れるかもしれない。
星の瞬きとまでは行かなくとも、丸い月が見れるだろうか。
シモツキ村で眺めたような、クレーターの影までクリアに見える月夜ではないだろうけど。
つい、気持ちが彼方に飛んでしまいそうになって、手にしたカトラリーを意味もなく
ナプキンで拭いてみた。
最近こうして、ふとした弾みにぼんやりとシモツキ村のことを思い出すことが増えている。
何の変哲もない、ただの田舎の。
ゾロの村のことを。
「いらっしゃいませ」
新しい客の到来を告げる声にも気はそぞろで、窓硝子を伝い落ちる雨の雫に目を奪われていた。
「予約はしてないんだが・・・いいかな?」
「はい、こちらへどうぞ」
―――あれ?
ゾロのことを思い出していたら、空耳まで聞こえるようになっただろうか。
なんだか、ゾロの声に似ている。
興味に引かれて視線を向けて、サンジは我が目を疑った。
傘を預けて濡れた肩を払っているおっさんの中に、ゾロの姿がある。
想いを馳せすぎて、とうとう幻覚まで見るようになってしまったのだろうか。
おっさんの中のゾロは、きょろきょろと首を巡らしてからサンジに視線を止めた。
「よお」
「え、マジで?」
つい地で声を出してから、慌てて取り繕う。
「あ、えっといらっしゃいませ。・・・どうしたんだ」
早足で近付き小声で返事する。
よく見れば見慣れない背広なんか着てるから、とてもあのゾロとは思えない。
「今日は仕事でこっち来てんだよ。皆も一緒だ」
促されて周りのおっさん達の顔をよく見た。
確かに、シモツキ村で見かけたことのある人ばかりだ。
「あ、こんにちは」
慌てて挨拶するサンジに、おっさん達は人懐っこい笑顔を見せて、口々に喋りだした。
「ご無沙汰してます」
「綺麗な店だあなあ。俺、入るのに緊張しちゃった」
それぞれ背広を着ているから、田舎で見たときとの印象が違っていてわからなかった。
「まあ、こちらへどうぞ」
入り口で溜まっているのに気付いて、サンジは奥のテーブルへと案内した。
丁度ランチのピークを過ぎてテーブルが空いて来たところだ。
「仕事って、なんの?」
連れ立って歩きながら小声で聞けば、ゾロもやや猫背気味に小声で答える。
「ファーマーズフェアってのがあるんだよ。農業を志す若者への集団説明会って奴かな。
それで、俺もこっち来てる」
「へえ」
なんだかわからないが、仕事関係でこっちに来たらしい。
サンジは水を配りながら、改めておっさん連中の顔を眺めた。
収穫祭の時に杵を振り上げてた人。
餅を丸める手際が良かった人
頭にタオル巻いて張り切っていたのに、結局酔っ払って全然役に立たなかった人。
「皆さんお揃いで・・・その節はお世話になりました」
「いいやあ、こちらこそ世話になったよ」
「今日は近くにサンちゃんのお店があるってゾロから聞いたから、是非行ってみようって
ことになったんだ」
「こんないい店だなんて知らなかったから、汚い格好してきて悪いね」
照れたように頭を掻くおっさんを前にして、サンジの方が畏まってしまった
「とんでもない。皆さんいつもと違う雰囲気で・・・カッコいいですよ」
メニューを開いて差し出すと、おずおずと受け取りしきりに瞬きしている。
サンジはゾロの側にそっと寄った。
「このランチコースAっての、みんなそれでいいな?」
ゾロが問い掛けると、云々と小学生みたいに揃って頷いている。
「んじゃこれ4人前。飲み物は水だけでいいや。コースだろうけどどうせ食うの早いから、
タイミングは計らないでどんどん持って来てくれ」
「かしこまりました」
「おい、ケーキは?」
この面子で場違いな台詞に、サンジは「ん?」と立ち止まった。
「サンちゃん、今日ゾロの誕生日なんだよ。だからなんかケーキねえかなあ」
「おいおい」
ゾロは額に手を当てて苦笑した。
サンジはぎょっと目を剥いて、ゾロに向き直る。
「何、今日ゾロの誕生日なのか?」
「ああ、まあ」
それは聞き捨てならない。
「わかりました、デザートの時に特製プレートをご用意いたします」
頼もしく言い切ると、おっさん達は嬉しそうに破顔した。
「ごゆっくりどうぞ」
サンジが一礼してその場から去ると、皆一様に頭を下げて身を縮こませている。
いかにも場違いなおっさん連中が、恐縮した面持ちで大人しく席に座っているのはなんだか
可愛らしかった。
「じじい、前にシモツキから送った野菜って、もう全部使っちまったっけ?」
厨房に顔を出すと、ゼフは背を向けたまま怒鳴り返してきた。
「なんでえ薮から棒に。んなもんとうになくなっちまったろうが」
「そっか」
やけに落胆した声色に、ゼフは怪訝そうに振り返った。
「いや、実は今シモツキの人らが来てんだ。わざわざうちに飯食いに来てくれたみてえ」
「お前が世話になったってえ人たちか?」
「ああ、ゾロもいる」
ゼフはふんと荒い鼻息を一つ出すと、隣に立つコックに指示を出しながら前掛けを外した。
「あ、Aランチ4名様バースディなんで、デザート俺にさせてくれ」
屈強なコック達の間を、サンジは蝶のように軽やかに通り抜ける。
その浮かれた足取りにちらりと視線を投げ掛けて、ゼフは表に顔を出した。
「いらっしゃいませ」
水で乾杯している所にやけに威厳のあるゼフが顔を出したので、ゾロたちはぎょっとして
動きを止めた。
「この店の料理長で、サンジの祖父です。いつも孫がお世話になっております」
「ああ〜」
「こちらこそ、どうも」
思わずその場で立ち上がりそうになって、椅子を中途半端に鳴らしながらおっさん達は
ペコペコと頭を下げる。
ゾロもテーブルに着いたまま、深く頭を下げた。
「たくさんの立派な野菜を頂戴して、ありがとうございました。店でも出させていただき
まして、非常に力強い味だと常連さんの間でも評判でした」
「不恰好な野菜ばかりで、お恥ずかしい限りです」
ソツなく答えるゾロの顔ばかりを、ゼフはそれとなく窺っている。
「市場にも出せない規格外のものでしたから、却ってたくさん送りつけてもご迷惑かと
思いましたが、あのような野菜でも活かして使ってくださってありがとうございます」
「こちらこそ、孫が突然押し掛けてはご迷惑ばかりお掛けしておりますのに、誠に申し訳
ない限りです」
ゼフは両手を太股に当てて、丁寧に頭を下げた。
ゾロも再び頭を垂れる。
「こっちこそ、遊びに来てくれる度に美味いものを食べさせて貰ってます。本当に、
腕のいい料理人ですね」
「いやあ、まだまだヒヨっ子で・・・」
ゼフは、恐らくはサンジも目にしたことがないような優しい眼差しで厨房へと視線を流した。
「今日はどうぞごゆっくりなさっていってください」
「ありがとうございます」
立ち去るゼフを、また男4人が中途半端に腰を浮かして深々と礼をしながら見送った。
着席してから、誰ともなくふうと息を吐いた。
「・・・なんか、凄そうなおじいさんだな」
「こっちに住んで長いんだろうな、流暢な日本語だ」
「サンちゃんが可愛くって仕方ねえんだろうなあ」
小声で話していると、サンジがワインを掲げて軽やかにやってきた。
「これは俺からのプレゼント。車とかには乗らねえんだろ?度数は高くないから、大丈夫だと思うぜ」
最後は、先月酔っ払って役に立たなかったおっさんに向かって言えば、後ろ頭を掻きながら
苦笑いしている。
「んじゃ、こちらが前菜。んでもってすぐメインを持ってくるから、適当に食っててくれ」
サンジの砕けた物言いで緊張が解けたのか、おっさん達は特別に添えられた箸を手にとって
元気よく食事を始めた。
「ご馳走様でした」
美味かった〜と腹を擦りながら、おっさん達はすっかり晴れ渡った空を見上げながら戸口に出た。
「美味かったよ、ご馳走さん。ワインもありがとう」
奢りなのに預かった金で自ら会計するゾロに、サンジは笑いながら釣りを返す。
「こっちには、いつまでいるんだ?」
「明日には帰る。午後もっかい説明会をやって、そのまま皆でS駅前のホテルで泊まりだ」
「楽しそうだな」
「まあな、最初からホテル代が勿体ないとか言ってんだぜ。部屋に帰って大人しく寝るはずが
ねえからよ」
サンジは一瞬寂しげな表情を見せたが、チンとレジを閉めて悪戯っぽく笑った。
「・・・都会の夜は危ねえぞ、ぼったくられんな」
「その為に俺がついてってやるんだよ。あいつら野放しにしたら、危なっかしくてしょうがねえ」
そう言えば、ゾロは元々都会出身だと聞いていた。
寧ろ田舎暮らしの方が慣れなくて不便だったろうに、サンジから見るとすっかり馴染んでいるから、
却って都会で見掛ける方が危なっかしく思えてしまう。
「そうだな、てめえのが本来は慣れてるんだろうが・・・」
サンジは戸口まで見送りに出ながら、ふふっと含み笑いをした。
「果たしててめえ自身が、ちゃんとホテルに戻れるのか不安だな」
「ああ?何言ってんだ。駅前だからすぐだろうが」
むっとするでもなく、呆れたようにそう返すゾロは、素で自分の方向音痴を自覚していない。
それが余計に可笑しくて、サンジは外で待っていたおっさん達に丁寧に頭を下げた。
「今夜はこいつを、無事にホテルにまで届けてやってください」
「おう任せといてくれ」
「その為に俺らは一緒に来たんだ、なあ」
口々にそう言って胸を張るおっさん達を前に、ゾロは初めて憮然とした表情になった。
「んじゃ、頑張れよ」
「おう、お前もな」
いつもはシモツキの駅で別れるときに言葉を交わすのに、今はそれが自分の店の前でだなんて、
なんだか不思議だ。
「サンちゃん、また遊びにおいでよう」
「美味しかったよ」
子どもみたいにぶんぶん手を振るおっさん達の頭一つ高いところで、ゾロが小さく会釈した。
窓際に立つゼフに気が付いてサンジは急に照れ臭くなったのだけれど、それを隠しながら手を振り返した。
